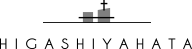2025/07/27
7/27巻頭言「教団出版局 『平和を継ぐ者に』―はじめに」その①
(実はこの夏二冊の新刊が出る。「希望のまちのつくり方」(西日本新聞社)に続き、日本キリスト教団出版局から発行される「平和を継ぐ者に―戦争証言・使命・祈り」の編集を依頼された。これは⽉刊誌『信徒の友』に掲載された戦争体験者の証⾔と戦後の平和活動の歩みから、戦後80年の今、平和を受け継ぐための使命を祈りつつ、あらためて考えるために9月に刊行される。私自身は『はじめに』を執筆した。以下は、その原稿である。)
私は、父が39歳の時に生まれた。次男とはいえ当時(1960年代)にしては遅く生まれた子どもだった。父は1926(大正15)年生まれ、出征し、生き延び、終戦を迎えたが、帰国はできずシベリアへ送られた。生死の境を何度もさまよい二年後帰国。それから大学、就職、そして結婚し二人の子どもが与えられた。小学校のクラスで親が戦争に行った子どもは私だけだった。その父も数年前に召された。
書斎の机は当時のまま置かれている。その引き出しの奥、麻の袋に入れられた木のスプーンが今もある。「麻の袋に木のスプーン」。なんだかお洒落な感じがするがそうではない。スプーンは荒削りで、袋は「ドンゴロス」と呼ばれる目の粗い麻を縫い合わせたもの。いずれも父がシベリアの極寒の中、生き延びるために自ら作ったものだった。戦後、父はそれを捨てることはできなかった。戦争体験について多くは語らなかった父だったが、退職後シベリアでの経験を自ら小さな冊子に書き残している。私には「戦争だけはあかん」と明確に繰り返し言っていた。
時折、実家に立ち寄る。父の仏壇にあいさつし、ドンゴロスの袋を手に取る。父が書き残したわずかな記録をたどりつつ、ドンゴロスと対話する。20歳の父がどんな思いで戦場に向かったのか。戦場で向き合った同世代の「敵兵」はどうだったのか。蹂躙された人々。シベリア抑留、そして帰国後の混乱。「戦争だけはあかん」と語る父の思いを直接聞くことはもはやかなわない。しかし、それでも私は時々ドンゴロスと対話をしている。そうしないと、再び戦争の渦中に引き戻されてしまうと思うからだ。
本書には27名の方々の証言、あるいは平和への思いが綴られている。編集者から送られてきた原稿に目を通した。正直「読解困難」な言葉が並んでいた。文章が難しいわけではない。「読む」ことはできる。それぞれの筆者は「思いを伝えよう」と丁寧に証言してくださっている。しかし、「読める」と「解る」は本質的に違う。それらの証言は「簡単に解った」と言ってはいけない言葉なのだ。それぞれの方が、その時、その場で経験された悲しみ、痛み、やるせなさ、懺悔を語られている。そして、それでもなお人には希望があると証しされている。「解った」と安易に言えない、言ってはならない。この困難な営みを経ずして、戦争にまつわる証言は継承されるはずはない。そういう意味で、本書は「読解困難な書」と言わざるを得ない。
つづく