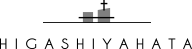2025/08/03
8/3巻頭言「教団出版局 『平和を継ぐ者に』―はじめに」その②
(実はこの夏二冊の新刊が出る。「希望のまちのつくり方」(西日本新聞社)に続き、日本キリスト教団出版局から発行される「平和を継ぐ者に―戦争証言・使命・祈り」の編集を依頼された。これは⽉刊誌『信徒の友』に掲載された戦争体験者の証⾔と戦後の平和活動の歩みから、戦後80年の今、平和を受け継ぐための使命を祈りつつ、あらためて考えるために九月に刊行される。私自身は『はじめに』を執筆した。以下は、その原稿である。)
戦後80年を迎える。これまで私は「読解困難」な言葉にどれだけ向き合ってきたのか、今さら問われている。ウクライナ・ロシア戦争、ガザでの虐殺、イランをめぐる危機的状況。「ファースト」という言葉が飛び交い、排外主義が跋扈する。多様性(ダイバーシティー)や公平性(エクイティ)、包摂性(インクルージョン)が蔑ろにされ、刺々しい空気が広がっている。
1901年、内村鑑三が「既に亡国の民たり」(『万朝報』)という文章を残してくれている。この頃、内村は足尾銅山事件に関わっている。
「国が亡るとは其山が崩れるとか、其河が乾上るとか、其土地が落込むとか云ふ事ではない、(中略)国民の精神の失せた時に其国は既に亡びたのである、民に相愛の心なく、人々互に相猜疑し、同胞の成功を見て怒り、其失敗と堕落とを聞て喜び、我一人の幸福をのみ意ふて他人の安否を顧みず、富者は貧者の救はんとせず、(中略)其教育は如何に高尚でも、斯の如き国民は既に亡国の民であって、只僅に国家の形骸を存して居るまでゞある」
(『内村鑑三全集9』内村鑑三、岩波書店、1981年、165〜166頁)。
120年以上前、苦しむ民と直面していた内村が遺した言葉は昔話にはならず新鮮さをもって私たちに迫ってくる。「我一人の幸福をのみ意ふて他人の安否を顧みず」。現在の世界に向けられた言葉だと思う。大国のリーダーに扇動されるように多くの人々が「我一人」を語り、世界は分断の危機に曝されている。この「自分病」とも言える病は、重症化し「戦争」という最悪の自体を生み出している。今日にこの内村の証言の意味は深い。
「自分さえ良ければ」が自分(自国)を保持するために有効だと多くの人が考える。結果、移民排斥などの動きが世界に広がっている。しかし、それが本当に「自分を守ること」になるのだろうか。そもそも「自分だけが生き残ること」などあり得るのか。「人が独りでいるのは良くない」(創世記2章18節)。これが天地創造における人間の本質である。「自分だけ」は、この人間の本質に反している。その先は「亡国の民」への道に他ならない。そんな時代にあって「亡国」の辛酸をなめた人々の言葉に向き合うことは大切だと思う。
つづく