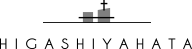2025/09/07
9/7巻頭言「『ファースト・こっからここまで』―そんな基準は一瞬にして変わる」最終回
「ファースト」という思考は、「こっからここまで」という枠組みを勝手に設定し世界の一部分を切り取っているに過ぎない。当初「ああ、これで自分は大事にされた」と安心しても、その中にあなたがいつまで入っていられるか誰も知らない。いや、実はすでに入っていないかも知れない。それが不安なら「こっからここまで」というやり方自体、つまりどんな形であれ「分断」や「区別」を正当化することを止める、あるいは認めないことだ。
かくいう私が生きてきたキリスト教会は、まさに「こっからここまで」の世界そのものだった。教会が語ってきた「こっからここまで」、それは「キリスト教徒だけが天国にいける」という思考である。これは差別である。そもそも神様はそういうことをなさるだろうか。そもそもそういうことをするならそれは神様だろうか。それは神でもなんでもないと思う。イエスは「私に従うものだけ救ってあげる」と言われない。「こうして、天にいますあなたがたの父の子となるためである。天の父は、悪い者の上にも良い者の上にも、太陽をのぼらせ、正しい者にも正しくない者にも、雨を降らして下さるからである。」(マタイ福音書5章)とイエスは語った。あるいは「『目には目を、歯には歯を』と言われていたことは、あなたがたの聞いているところである。しかし、わたしはあなたがたに言う。敵を愛し、迫害する者のために祈れ。」(同上)とも説いた。なによりも自分を十字架にかけた人々のために「父よ、彼らをおゆるしください。彼らは何をしているのか、わからずにいるのです」(ルカ福音書23章)と祈った。イエス・キリストの十字架の恵みは、キリスト者にのみ与えられたのではない。私は、神(神の子)は「こっからここまで」とは決して仰らないと信じている。「それだけは言えない」という神の不自由さこそが愛の本質だと言える。東八幡キリスト教会は「こっからここまで」という教えを捨てた。神は、すべての人、すべてのいのちを愛してくださる。そうでないなら神ではない。
「分断」の根底には「不安、不満、怒り」がある。「ファースト」を語る人はそれを利用したに過ぎない。この「不安」がどのように蓄積されたのか、それをどう解消するのか。それが重要なのだ。あの時ドイツは、第一次大戦の敗戦国として負わされた賠償金や一九二九年の大恐慌の中で民衆の不満と不安、怒りがナチズムを生んだ。さらにワイマール憲法によって確立された国民主権や共和制、男女平等などの民主主義が攻撃対象となった。同時期、日本でも大正デモクラシーが否定され軍国主義が育っていった。今日、世界で、そして日本で不安と不満、怒りが限界に達しつつあるのかもしれない。だが、だからと言ってその「はけ口」を弱い立場の人々に向けてはいけない。不安や不満を敵愾心でごまかすのではなく、その根本問題である格差や貧困を改善することが何よりも重要なのだ。
「ファースト」は「こっからここまで」ということに過ぎない。そんな基準は一瞬にして変わる。外国人差別を容認すれば、次は別のマイノリティーが「はけ口」になる。「排外」主義は直ぐに「排内」主義に転じるだろう。津久井やまゆり園事件とは何であったのか。あれから九年が経ったが、私たちは、この事件の意味を問い続けなければならない。犯人は「意味のあるいのち」と「意味のないいのち」を分断し、「意味のないいのち」と見なされた重複障害者を虐殺した。あの犯人自身、その分断線のどちら側に立っていたのか。私はあの事件以来考え続けている。
「こっからここまで」という考えが何を生み出すのか。私たちはその「端緒」に今立っている。この先にどんな「結末」が待っているのか。私たちは歴史の教訓から学ぶため一旦立ち止まりそれを考えなければならない。「そのときにはすでに手遅れであつた」というニーメラーの悔悟を繰り返さないために。