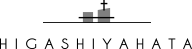2025/09/21
9/21巻頭言「泣ける教会―創立70年宣教」その①
世界のあちこちで分断が進んでいる。ロシア・ウクライナ戦争、イスラエルによるガザでのジェノサイド。国内ではヘイトスピーチ、「ファースト」に熱狂する人々、そして排外主義。私たちは、その現実を日々の報道によって知らされている。
しかし、分断の現実は、実はそれらの場所で起こっているわけではない。分断の現実は、私の中で進行している。分断は内在的な現実として私の自身の中に存在しているのだ。なぜ、そう言えるのか。理由は明確だ。そのような世界の現実に日々接しているにもかかわらず私は泣いていない、わたしは泣けないからだ。この事実こそが、世界と私が分断されていう現実を証明している。
ガザではこの瞬間にも子どもたちが殺されている。爆弾の餌食にならずとも、明日は飢え死にするかも知れない子どもたちや人々がいる。ガザでの死者は6万人を超え、その内1万8,592人が子どもだという。そんな現実が今日も繰り返されているにもかかわらず私は泣けていない。分断は、ヨーロッパ、中東、アメリカ、そして日本で起こっているのではない。ましてやテレビやインターネットの中で起こっているのでもない。それは「泣けていない私」の中に現に存在しているのである。
今日、東八幡キリスト教会は創立70年記念感謝礼拝を迎えた。私たちは70年のテーマとして「笑える、泣ける、生きる」を掲げた。パウロはローマ書において「喜ぶ者と共に喜び、泣く者と共に泣きなさい」と語っている。しかし、現在の世界の現実は真逆だ。
内村鑑三は1910年に「既に亡国の民たり」という文章を残している。内村は「国が亡びるとは、山が崩れるとか、川が干上がるとかではない。国民の精神が失せた時に国は滅びたのである」と指摘した。では「国民の精神の失せた」とはどのような事態であるのか。「お互いに愛し合う心なく、互いに疑い合い、仲間の成功を見て妬み怒り、失敗と堕落を聞いて喜ぶ。自分一人の幸福だけ考えて他人のことは考えない」。それが「精神の失せた」現実であり、そういう民はすでに亡国の民であると内村は言う。120年以上前の文章であるが今日この時代に生きる私たちは、この言葉に真摯に向き合わねばならない。
泣く者と共に泣くのではない、泣いている人を見て嘲笑する。喜ぶ者と共に喜ぶのではない、喜ぶ人を見ると嫉妬する。そして、自分だけ、自国だけの幸福を追求する。これが亡国の民である。私たちは、「自分とは違う」と胸を張れるだろうか。
「泣ける」ということはどういうことであろうか。それは「人間である」ということだ。作家の灰谷健次郎は「太陽の子」の中でこのように書いている。「いい人ほど勝手な人間になれないから、つらくて苦しいのや。人間が動物と違うところは、他人の痛みを自分の痛みのように感じてしまうところなんや。ひょっとすれば、いい人というのは、自分の他にどれだけ自分以外の人間が住んでいるかということで決まるのやないやろか」。他人の痛みを自分の痛みのように感じることができるのが人間であると灰谷はいう。他人の痛みを痛み涙する。それが人間である証し。と、するならば泣けないというのは、果たして人間であるかどうかが問われる事態なのである。
つづく