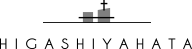2025/11/16
11/16巻頭言「希望とは何か⑥―生の絶対的価値 その①」
生の絶対的価値 希望は「可変性への信頼」であると先に述べた。しかし、実はそれだけで希望を捉えるには問題もある。矛盾したことを言うことになるが、一方で「絶対的で変わらない」あるいは「変わらなくてもよい」「変えてはいけないもの」はある。つまり「可変性」ではなく「不変性」もまた希望にとって大切な要件なのである。
長く「支援」の現場に携わってきた。助けが必要な時、誰かが支援をしてくれる。現在の状況から抜け出したい、現状を変えたいと思う時に誰かが手を差し伸べてくれる。これは本当にありがたい。ただ「支援」という言葉には「棘(とげ)」があるようにも感じてきた。それは「支援」には「あなたはそのままではいけない」、「早く変わりなさい」という「圧」がつきものであるからだ。支援を受ける人は「変わらなければならない」と、支援をする人は「変えなければならない」と、お互いがプレッシャーの中に身を置いている。これは時に暴力的にさえなる。
2002年に国会で「ホームレス自立支援法」が成立した。その後、様々な施策が実施され当初2万5千人を超えていたホームレス数は、現在3千人を下回った。北九州においても2004年に公設民営型の「自立支援センター北九州」が開設され、現在では市内でホームレス状態の人をほとんど見かけなくなった。
先に述べたように「ホームレスからの自立」ということに多くの人々が懐疑的であったが、しかし、実際に「自立支援」が始まると多くの方々が「自立」を果たされた。私たちは、それに勇気をもらい「人は出会いによって変わる」とことを確信した。だから「ホームレスからの自立は可能」と世間、何よりも行政に訴えた。世間の予想を裏切り「ホームレスからの自立」は成果を上げていった。
そもそもあったホームレスに対する偏見や差別への「抵抗」もあり、私たちは「自立できる」、「人は変わる」ということを強調していた。それをもって世間の認識を改めようとしていたのだ。当時の資料には「自立率9割以上」「就労自立率9割以上」「自立継続率9割以上」という「成果報告」が目立つ。しかし、ここに落とし穴があった。
つづく