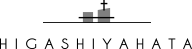2026/01/04
1/4巻頭言「希望とは何か⑪ ―外在性への委ね その②」
当初炊き出しは、おにぎり二つと豚汁、ゆで卵を携え路上で暮らす人々を訪ね歩いた。それは食料支援と共に大切な出会いの場面でもあった。今もこの活動は続いている。
しかし、お弁当を配るだけでは埒が明かないのも事実。野宿とは、すべてを失った状態である。一旦野宿状態になるとそこから這い上がることは難しい。住所が無いと不動産契約も求職の手続きも、さらには生活保護の申請さえも認められなかった(これは当時のことで北九州市は現在は路上から申請も認めている)。だから活動は必然的に住宅確保や就労支援など「自立支援」へと向かっていった。
家が無い人には家を、仕事がない人には仕事を。だが野宿状態であることを承知でアパートを貸してくれる大家さんを見つけるのには苦労した。それでもようやく大家の了解を取り付け「アパートの準備が出来た」ことを路上の人々に告げて回った。その知らせに路上の百人が百人とも「待ってました」と立ち上がると思っていた。しかし・・・。
「考えとく」「今度でいい」「放っておいてくれ」「せからしい(鬱陶しい)」。そんな反応を示す人が少なくなかった。「全員がすぐさま立ち上がる」との私たちの予測は大きくハズれた。最貧困状態であるにもかかわらずなぜ彼らは立ち上がらないのか。
当初は、物件の条件が悪いのが原因だと考えた。確かに当初の物件はどれも古く、長い間空き家だったものが多かった。しかし、数年経ち徐々にではあるが比較的新しい物件も紹介できるようになった。就職にしても同様で、当初は給料の安い、あまり人気の無い職種が多かった。その後の人手不足もあり、それも徐々に解消していったが、路上の人々の反応は相変わらずだった。何が足りないのか。条件か。違う。絶望しているからだ。あるいは希望が持てない、すなわちもう一度生きようとする「その気」が無いのだ。つまり「動機」が足りていない。ではその「生きる動機」はどこからくるのか。
第一に、自分自身の中からそれは起こる。「内発的動機」である。「良い暮らしがしたい」。「美味しいものが食べたい」「自動車が欲しい」「旅行に行きたい」「結婚したい」など、自分が望むことが明確にある時、人はそれ故に頑張ることが出来る。
しかし、人生には自分の中が空っぽになる日がある。野宿のTさんと初めてお会いした日、彼は野宿生活が苦しいことを訴えつつ「私は毎晩お祈りしてから寝ています」と語られた。私は牧師である。「お祈りですか。もしかしてクリスチャンですか」とお尋ねすると彼は「いや、こんな状態ですから、もはや神も仏もおりません」と答えられた。ならば何を祈っているのかとお尋ねするとTさんは静かにこう答えられた。「もう二度と目が覚めませんようにと寝る前に祈るのです」。自分で死ぬ勇気はない。だからこのまま目が覚めない、つまりこのまま死ねるのならその方が良い。確かに「絶望は死に至る病」である。こういう「内発的動機」が潰えた状態、それを絶望という。
つづく