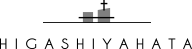2025/10/12
10/12巻頭言「希望とは何か①―はじめに」
「希望のまち」が動き始めたのは2019年秋の事だった。その後、資材高騰、コロナ禍、円安、労働力不足など予想だにしない事が起こり計画は遅れに遅れた。当初四階建で10億円の計画は、最終的には3階建で16億円近くとなり、最初の入札は不調に終わった。だがこの困難を上回る支えが全国から届き、2025年1月ついに着工にこぎ着けた。感謝に堪えない。来年夏の竣工に向け工事は順調に進んでいる。
この間、しばしば問われたことがある。「なぜ、『希望のまち』と名付けたのか」。「協議を重ね熟慮した」とは言い難い。あの時、あの風景の中で私の中に浮かんだのが「希望」だった。いや、「浮かんだ」というよりも「与えられた」という感覚に近い。それは「天啓」のようなものだった。それで「希望のまち」と命名してしまった。
だからこの5年間、「後追いの形」で「希望とは何か」を考え続けることになった。希望とはなにか。希望を持つとはどういうことか。希望はどこにあるのか。まち開きまで一年を切った。「希望」について今の思いを書き残したいと思う。「まち」は生き物だ。生きている人間の集まりだからだ。懸命に生きようともがく人がいる。絶望の中でなんとかしのいでいる人がいる。生きる喜びに満たされた人がいる。まちは、そうした「生きている人」によって構成される。ゆえに「まち」自体も変化し成長していく。生きているのだ。だから、ここで「希望とは」と書いたとしても、それは「固定」されない。ことばは「希望のまち」が生きている限り更新されていく。ともかく「今の時点で」という思いでことばを残す。「まち」の担い手が変わっていく中で「希望」についてのことばも変化していくのだと思う。
まずは「希望のまちプロジェクト」の経緯について簡単にまとめておく。抱樸の使命(ミッション)は三つ。「ひとりの路上死も出さない」。「ひとりでも多く、一日でも早く路上からの脱出(自立)を」、そして「ホームレスを生まない社会の創造」。活動開始以来、これを使命として活動を続けてきた。37年の活動で路上死は無くなり、路上から自立された方は3,800人を超えた。市内ではホームレス状態の方をほとんど見かけなくなっている。たとえ見かけたとしても早い段階で自立支援を実施できている。
活動が始まって20年が経過した2008年9月。世界は「金融危機」に見舞われた。「リーマンショック」である。東京では「日比谷派遣村」が始まり、派遣切りや雇止めをされた人々が身を寄せていた。その年の暮れ北九州でも若者が路上に現れた。
つづく