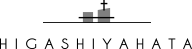2025/10/19
10/19巻頭言「希望とは何か②―はじめに」
戦後の日本社会は、「長期雇用慣行」に裏付けされた「中間層」が基軸となった社会だったが、1990年のバブル崩壊後「大学卒業一括採用、終身雇用」という「日本型雇用体制」は瓦解した。この時の就職困難者は「就職氷河期世代」と呼ばれ推計で1,700万人とされている。既に50代になっている人もおり、今後無年金のまま老後を迎えざるを得ない人も出て来ることが懸念される。社会や経済の構造が大きく変化していく中で不安定な就労を強いられる人が増加し、その結果、生涯未婚や単身世帯も増加した。つまり、日本社会の基礎構造である「家族・身内がいること」が前提とならない人が増えた。
これまで抱樸が出会った路上生活者の大半は単身、あるいは家族との縁が切れた人々だった。例えば亡くなったとしても家族が葬儀などを引き受けてくれる人は一割もいなかった。だから、当初から家族が果たしてきた機能をいかにして社会化するかが必然となった。「経済的困窮からの脱出」と「家族機能の社会化」は抱樸の活動の本質だと言える。
これら路上の人々に見られた課題が社会全体に広がっていることが明らかになったのがあのリーマンショックだった。抱樸の第三の使命である「ホームレスを生まない社会の創造」は「路上生活者を生まない」という事に留まらず「ホームレス=社会的孤立をいかに防ぐか」を意味する時代となっていたのだ。
2000年のNPO法人化の折に私は理事長就任あいさつとして「一日も早い解散を目指す」と語った。それは「このような困窮者支援のNPOがいつまでも必要とされる社会ではいけない」と思ったからだ。しかし、上記のような日本社会の構造変化は、「常態化した構造的問題」に対してどう対処するのかを考えざるを得ない事態を招いた。それまで「NPO法人北九州ホームレス支援機構」との名称で活動してきたが、あるべき社会を創造するために「抱樸(条件をつけず荒木原木を受け止めるつながり合える地域社会の創造)」と名称を変更し「解散しない」、いや「解散できない」ことを宣言した。
リーマンショック後、抱樸は2010年以降、社会づくり、まちづくりに取り組むようになる。その第一歩が「抱樸館北九州」建設だった。これは単なる施設建設に留まらず「抱樸村構想」として進められた。つまり、新しい共生型の地域づくりである。約一年におよぶ住民反対に晒されながらも2013年9月無事開所することができた。振り返るとこの時の経験が今回の希望のまち建築にも役立ったように思う。
つづく