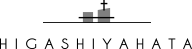2025/09/14
9/14巻頭言「あの日ガリラヤ湖で―『こっからここまで』を超える 創立70年もう一つの宣教」
東八幡教会創立70年感謝礼拝の宣教とは別に「もうひとつの宣教」を残しておきたい。
「ファースト-あなたが一番」という言葉が踊る時代に私たちは生きている。民衆を誤導する政治家は問題だ。しかし、なぜあの言葉が人々に響いたのか、それを考えることは大切だと思う。「自分は捨て置かれた。自分のことなど誰も気にかけてはいない」。そんな悲しみと不安、不満が積み重なっていたと思う。例えば「就職氷河期世代」と放置され続けた人々がいる。そんな時「あなたが一番」という言葉が「希望と救い」に聞こえたとしても不思議ではない。誤導する政治家たちは、そのような現実を作ったのではなく、利用したに過ぎない。だから、この現実がどうして生まれたのか、それを考えねばならない。
さらに「外国人が優遇されている」というデマが敵愾心を煽った。このような対立と分断は、米国、ヨーロッパ、そして日本において広がっている。悪しきポピュリズムが増殖している。
聖書にこんな話がある。イエスと弟子が舟に乗ると激しい暴風が起こり舟は波にのまれそうになった。弟子たちは寝ていたイエスを起こし「死にそうだ」と訴える。イエスが風と海を叱ると大なぎになり弟子たちは助かった(マタイに福音書8章)。さて、今日この時代に、この奇跡をどう読むか。嵐の海で死にそうだった弟子たちは、イエスによって九死に一生を得る。イエスに従う弟子たち、あるいはキリスト教会という舟に乗っている人々は救われる。それがこの箇所の意味だろうか。違うと思う。
「ファースト」という言葉は「こっからここまで」を意味する。日本人だけ、アメリカ人だけ、という発想は容易に排外主義に結びつく。しかし「敵(とされる存在)」は外国人に留まるとは思えない。「排外」は「排内」へと向かい「性的マイノリティ」「障害者」「困窮者」、そして「民主主義」が「敵」となる。「ファースト」が普遍的でないかぎり、すなわち「いのちファースト」とか「みんなファースト」でないかぎり「こっからここまで」にあなたがいつまで入っていられるか解らない。いや、既に入っていないかも知れない。
嵐の海で助かったのは誰か。イエスと一緒の舟に乗っていた弟子たちだけか。違う。その時ガリラヤ湖上にはどれだけの舟がいたのだろう。暴風は湖面のみならず沿岸の集落をも襲っただろう。あの日ガリラヤ湖では弟子たちの「死にそうだ」という声と共に他の人々の悲鳴が響いていた。風と海をイエスがどんな風におしかりになったのか知らないが「ええかんげんせえ」というイエスの声はガリラヤ湖周辺、いや全世界に響きわたった。そして世界は大なぎとなった。
イエスと一緒にいた弟子だけではない。あの日ガリラヤ湖にいたすべての人が救われたのだ。イエスの言葉は「こっからここまで」と人を籠絡(うまく丸め込んで思い通りに操る)に対する「叱り」でもあった。私は今日、この時代においてあのガリラヤ湖の奇跡をそのように読みたいと思う。
東八幡教会は「こっからここまで」を止めた。「キリスト者だけが救われる」という差別を廃したのだ。暴風が吹くすさぶ今日の世界において「敵意という隔ての中垣(エペソ2章)」を取り除く。次の70年に向けた教会の使命としたい。祈る。