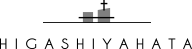2025/11/02
11/2巻頭言「希望とは何か③―可変性への信頼その②」
だが一年が過ぎ、二年が過ぎる中で「変わっていく人」が現れた。寝る前「二度と目が覚めませんように」と祈っていた人が「アパートに入りたい」、「自立したい」、「働きたい」、「もう一度生き直したい」と言い始める。驚いた。一人が変わると後を追うように「俺も、俺も」と続く人が現れた。結果、37年間で3,800人が路上から脱し新たな生活を始められた。人は出会いによって変わる。私たちは、そんな確信を得た。
そんな「可変性への信頼」を僕に強烈に示した人がいる。西原宣幸さんである。先に述べた通り、リーマンショックの後、私たちは名称変更(抱樸)と共に「地域づくり」へ活動を広げようとしていた。「抱樸館北九州」建設である。それまで活動を温かく見守ってきた地域から反対の声が上がった。住民反対運動は広がりを見せ、私たちは建築工事開始を延ばすことにした。「地域づくり」において住民の理解は何よりも重要だったからだ。その後、8か月にわたり17回の住民説明会を開催した。だが、毎度会場では「ホームレスは危険」「障がい者は危険」「やるんだったらどこか遠くでやれ」など偏見と差別に基づく心無い言葉が飛び交った。
13回が終わった頃だったと思う。「もう私(支援者)の言葉では説得できない」と思った。だから野宿を経験し、その後立ち上がり、今は地域で仕事をしながら暮らしている2人の「当事者」に来てもらうことにした。先述のごとく差別的な言葉が飛び交う場所に当事者が立つ。単に彼らを傷つけてしまうかもしれないという心配があったが、他に手がなかった。
引き受けてくださったのは、西原宣幸さんと下別府為治さん。西原さんは11年、下別府さんは6年の野宿生活を経験されている。自立後、仕事に就き地域で暮らしておられる二人から野宿生活のこと、自立に至った経緯、そして現在の思いなどを語っていただくこととした。当時、会場は少し緊張した空気となった。そして、二人はそれぞれ話しはじめた。会場は静まり返った。話が終わった瞬間、拍手が起こった。「ああ、これで終わった」と私は安堵した。しかし・・・。
つづく