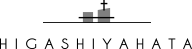2025/12/28
12/28巻頭言「希望とは何か➉ ―不解性への耐性 最終回 外在性への委ね①」
長い学校教育の期間においても私たちは「問い」よりも「答え」を重んじてきた。「必ず正解がある」が前提。テストの度に「ただ一つの正解」を的確に書くことが求められた。書けた人が「優秀」とされた。
だが一旦社会に出ると世界はそう単純ではなかった。何が「正解」か、わからない。そんな日々の現実をさまよい歩く。「解ったら生きていける」と考えていては生きていけない。「解らなくても生きる」。不可解を生きる。それが生きることだった。
答えは明確ではない。目的も希望も不可解で隠されている。大切なことは隠されている。この不可解に耐えうるか。それが希望を捜す人に求められることである。「不可解性への耐性」。それが希望には欠かせない。
「信仰」に近い感じがする。「良く解らないがある」と信じること。「隠されている」とは、実は存在しているということを示している。だから捜す。端(はな)から「無い」と思っている人は捜さない。私たちは、不可解の深淵に向き合い、それでも捜し続ける。不可解性に耐えながら私たちは捜し続ける。それこそが希望にとって不可欠な態度なのだ。
⑤希望とは何か―外在性への委ね
人はいつ絶望するのか。それは「その人が絶望した日」。「本人次第」。自己責任論の時代、絶望をそう考える人は一層増えているように思う。しかし、そうだろうか。
実存主義哲学のゼーレン・キルケゴールは「絶望は死に至る病」であるとした。キルケゴールが言う「絶望」は、「本当の自分であろうとする自分から目を背けた状態」を指すが、中でも「罪としての絶望」ということを語っている。これは神ということを考えつつも絶望したままでいるという状態を意味する。キルケゴールは、「死の病」から逃れるためにキリスト教信仰が必要だと考える。それは神の前で自己自身であろうと欲することであり、神との関係の中で自己を再構築することだと言える。絶望という死に至る病を経験した中で、絶対的な他者である神を見出し、自分を見つめ直すことで希望を見出す。希望は、自分自身の中でのみ醸成されるのではなく、外に存在する他者(神)との関係の中で見出される。そのような「関係」の中で人は希望を見出すし、そういう関係が途切れると「死に至る病」に取りつかれる。
つづく