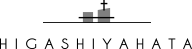2025/05/04
5/4巻頭言「調べられることは覚える必要はない―AIの時代を生きる『支援者』」①
路上に暮らす人々への支援が始まったのは1988年。コンピューターが普及する七年前「Windows95」はまだ無かった。その後、インターネットが使えるようになるが、今のようにサクサクとは動かず根気よく画面を見つめていた。
当時の北九州市は生活保護申請、特に路上からの申請を受付けなかった。これは明らかに申請権の侵害に当たる。後に申請を拒否された30代男性の「おにぎり食べたい餓死事件」が起こり現在では大幅に改善されている。
コンピューターが自由に使えるようになる前、役所との交渉は「素人の私たち」にとって相当に骨が折れた。「素人」というのは生活保護法を特に勉強したわけではなく、その運用や関連する制度にも詳しくない一般市民として交渉に臨むわけだから当初は役所が説明する言葉がそもそも解らないという有様だった。
「これではいけない」とこちらも勉強をするようになった。『理論武装』と言えば勇ましいが、ともかく本を読んで頭に入れることが重要だった。役所側から「こんな支援が受けられますよ」という親切なアドバイスはなく、こちらが「ここに書いてあるではないか」と迫るしかない。片手に「生活保護手帳」、片手に「生活保護問答集」(どちらもケースワーカーが業務で使う本)を携え役所に向かう。妙な言い方だが「知ってる者勝ち(知らないとごまかされる)」が現実だった。今から考えると「知らないと使えない、使わさない」こと自体が問題で、勉強せずとも利用できる制度の相談窓口があれば良いだけの話。しかし当時は相当苦労した。
その頃「教授」と呼ばれた方がいた。彼は野宿生活をしながら図書館に通い、生活保護法を熟知していた。交渉中、役所側がごまかそうとあれこれ言い出す。教授は「それについては保護法何条にこうります」とか「問答集でこのように説明されています」と反論する。頼もしい。「生きるための学び」そのものだ。「本当の知識」とは何かということを教えられた。
その後技術はものすごいスピードで進化した。インターネットの通信速度は急激に上がり、スマートフォンが登場した。片手に百科事典、いやそれ以上の情報を持ち歩くことが可能になった。記憶力で勝負することは減り(とはいえ、まったく知らないとネット検索はできないが)「支援者としての仕事の仕方」は変更を迫られた。かつて攻防戦となった『知っているというマウント(相手より優位なポジション)』の取り合いで勝負しなくてもよい。解らないことはその場で調べれば済むようになったのだ。
つづく