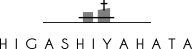2025/05/11
5/11巻頭言「調べられることは覚える必要はない―AIの時代を生きる『支援者』」②
僕自身の日常も変化した。国の審議会や検討会議に出席することが多いが、正直言って『解らない用語』が飛び交う。周りはそうそうたる学者の方々で、とてもついていけない。そんな時は机の下でスマートフォンを使って即検索。「あああ、なるほどそういうことね」と理解する(うわべだけだけど)。そして何食わぬ顔で「ハイ」と手を上げ『10年前から知ってました』という顔つきで「それについては、こうこうこうです」などと発言する。いや便利、便利(それでいいのか?)。
今後、技術はますます進化するだろう。となると支援における支援員の働きはずいぶん変わることになると思う。これまで支援員は、相談者からヒアリング(聞き取り)をし、アセスメント(分析・評価)を元に『主訴』の確定、そして必要な個別支援計画(プラン)を立て実行する。大切なのは「その人に合った支援計画を立てる」ということと必要な制度に結び付けるということ。当然のことだが、それには制度に関する知識が必要となる。支援計画を立てる上で「知識」は何よりも重要だ。不勉強な支援員にあたると使える制度も使えなくなる。法律は定期的に改正されるし、それに伴って運用の規定も変わる。しばしば「通知」が本省(厚労省など)から発出される。時には新しい法律が整備され制度が始まったりもする。支援員はそれを知った上で「最新の情報を踏まえた支援計画」を提示しなければならない。だから研修や勉強は欠かせない。
ただ、今後ネットを活用した検索機能が飛躍的に向上するとどうなるか。生成AI(人工知能)はすでに実用段階に入っている。こうなってくると『すべてを覚えること』はどこまで必要かが問われることになる。アインシュタインは、「調べられることは覚える必要はない」と言った。コンピューターの無い時代、アインシュタインはすでにそう考えていた。彼は天才だからそうかも知れないが、AIの登場は天才ではない私でさえ「そうかもな」と思わせてくれる。これまで支援員が「良い意味」でも「悪い意味」でも「独占」してきた制度の知識は、今や誰でも瞬時に調べられる(誰でもと言ってもコンピューター等の環境を持っている人といない人の格差は広がっているが)。
今後は生成AIが支援計画を創ることも当然あり得る。「悪い意味でも独占」と書いたのは、お金や権力のみならず「知識」においても「持っている側が上に立つ」ことが起こり得るからだ。『知っているというマウント』は、動きが悪い行政を動かす場合はともかく、支援においては「支配-被支配の関係」を生み出すことになりかねない。つまり知っている支援者が支配的になる。いわゆる「パターナリズム(父権主義:悪気がなくても強い立場の者が弱い立場の者の利益のために、その人の意思に反して行動に介入、干渉すること)」に陥る。『知っているというマウント』は支援現場でも起こり得る。誰でも自分で調べられ、AIに意見を聞ける時代となれば、そういうことも減る。
つづく