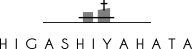2025/06/29
「信じ、弱く、愛し、近づく―この時代を生きるための信仰的課題」その⑥
(これは2025年度計画総会の日に為された宣教を補足修正したものです。)
パウロもまたキリストにおいて示された愛についてこう語っている。ローマ人への手紙5章6〜8節 「わたしたちがまだ弱かったころ、キリストは、時いたって、不信心な者たちのために死んで下さったのである。正しい人のために死ぬ者は、ほとんどいないであろう。善人のためには、進んで死ぬ者もあるいはいるであろう。しかし、まだ罪人であった時、わたしたちのためにキリストが死んで下さったことによって、神はわたしたちに対する愛を示されたのである。」 キリストが十字架に架かられたのは私たちが優れていたとか、信仰深かったということでは決してない。私たちはただ弱かった。不信心で、何よりも罪人だった。すなわち「ディール(取引)」できる材料を何一つ持ち合わせてはいなかった。にもかかわらずイエスは私たちのために十字架に架かり、私たちに対する愛を示されたとパウロは言う。ここにあるのは愛のみ。しかもそれは無償の愛だと言える。
パウロは、なぜ、それほどに神からの一方的な愛に着目するのか。彼がまだサウロと呼ばれていた時、彼はキリスト教徒迫害に息を弾ませていた。しかし、その後、復活のイエスと出会い彼は悔い改める。迫害者であった自分をイエスは使徒として抜擢されたのだ。本来ならパウロは、その行った残虐な行為によって裁かれて当然であった。彼は神との間で「ディール(取引)」できる材料、すなわち神に認めてもらえるような材料を何一つ持ち合わせてはいなかった。迫害者であり、人殺しの自分が赦されて生きる。そこにあったのは愛のみだった。キリストはただただパウロを愛された。だから彼はキリストの愛に着目せざるを得なかったのだ。
コリント人への第一の手紙13章4〜13節においてサウロは愛とは何かを語る。有名な「愛の賛歌」である。 「愛は寛容であり、愛は情深い。また、ねたむことをしない。愛は高ぶらない、誇らない。不作法をしない、自分の利益を求めない、いらだたない、恨みをいだかない。不義を喜ばないで真理を喜ぶ。そして、すべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてを耐える。愛はいつまでも絶えることがない。(中略)このように、いつまでも存続するものは、信仰と希望と愛と、この三つである。このうちで最も大いなるものは、愛である」 愛は自分の利益を求めない。自分だけ良ければいい。自分第一。自国第一。そこには愛はない。なぜなら愛は自分の利益を求めないからだ。そして最後に残るものとして、パウロは信じること、望みを抱くこと、そして愛を挙げ、その中で最も大いなるものは愛だと宣言する。罪の現実を生きてきたパウロは、そう宣言するしかないことをよく知っていた。
NPO法人抱樸には「ほうぼくボランティア宣言」というものがある。その中心テーマは「やっぱ愛だよね」という言葉である。条件をクリアした人、資格のある人だけが助けてもらえるのではない。もしそうならば誰が抱樸の支援を受けることが出来ただろうか。支援する側にしてもどれだけ頑張っても所詮罪人の活動、つまり不完全な行為であり、時に相手を傷つける。支援する側もされる側も、いずれにしても無条件に赦されているという神の愛を認識するしかない。だから抱樸の活動は「愛」によってのみ成立する。「やっぱ愛だよね」。パウロも抱樸もそれを自らの事柄として宣言してきた。「ディール(取引)」によって分断されつつある世界の只中でこの宣言を声高に響かせる。それこそが東八幡キリスト教会が担う伝道なのだと思う。
つづく