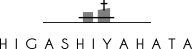2013/03/21
生笑一座(いきわらいちざ)誕生秘話
二〇一三年三月、生笑一座は誕生した。なぜ生笑一座は生まれたのか。その理由(わけ)について以下に記録することとする。
そもそも生笑(いきわら)とは何か。生笑とは、「生きてさえいればいつかきっと笑える日が来る」という言葉からとった。二〇一一年三月一一日、東日本大震災が起こった。私自身も直後から支援に関わっていた。三月末、被災地に入った。私たちの活動方針は「最も小さくされた人々に偏った支援を行う」という、少々変わったものだった。この方針の元、最初に入ったのは、石巻市の先、牡鹿半島に点在する小さな漁村集落の一つ、蛤浜であった。九所帯しかない集落だったが津波で五軒が流されていた。最初に出会ったのは区長さんの亀山夫妻。亀山夫妻は、訪れた私たちを歓迎下さり、九州から届けられていた物資を大変喜んで下さった。
亀山さんは主にカキの養殖をされていた。しかし、今回の津波で船もカキ筏も、いや港自体が無くなっていた。「私たちは、今回の津波ですべてを失いました」と亀山さんは、涙ながらに話された。こちらが返事に詰まっていると亀山さんは「昨日着いた荷物の中にこんなものがありました」と絵手紙を見せて下さった。その絵手紙の中に「生きてさえいればいつか笑える日が来る」という言葉はあった。その時、「私たちはすべてを失いましたが、今日はこの言葉で生きています」と亀山さんが仰った。「生笑」は、あの極限状況の中で出会った言葉だった。
その後、震災支援とホームレス支援に奔走する日々が続いた二〇一三年三月。私は、一つのことを悩んでいた。ずいぶん以前から小学校や中学校に呼ばれてホームレスに関する授業を依頼されて行っていたが、ある時からこれでいいのかという疑念が自分の中で広がっていった。それは、授業でホームレスについて語っている自分は、本当の冬の寒さも知らない、ひもじさも知らない、つまり野宿を経験したことのない人間であった。そんな自分が子どもたちの前でホームレスについて語っている。この言葉の限界を感じていた。
時を同じくして私は、北海道浦河のベテルの家の活動に出会っていた。「当事者研究」と呼ばれるその活動は「自分が自分の専門家」という彼らが生み出した言葉に象徴されるように、まさに精神障がいを持つ当事者が自己を分析し、自分に対する対応を決めていく。この当事者主権がもつ原則性と力に圧倒されていた。
そんな中で、子どもたちの前で野宿経験のない自分がホームレスについて語ることはなんだか嘘をついているような気持ちさえしていた。しかし、一方で小学生時代にホームレスの現実と触れること自体には大きな意義がある。特に子どもによるホームレス襲撃事件、あるいは子どもの貧困の現実からしても、この課題は子どもたちにとって大切であることは間違いない。だから、止めるわけにもいかず悩んでいたのだ。
そこで、ホームレスから自立された当事者の互助組織である「なかまの会」の役員会に出向き、その旨をお伝えした。そして、当事者のことばが必要だという呼びかけに応じて下さったのが、現在の生笑一座のメンバーである。
二〇一三年四月「おけいこ会」が始まった。まずは、一座結成の目的や何を伝えるのか、ホームレス生活にまつわる事象の実演はどうか、などアイデアを出し合った。現在では、導入(自己紹介)の後、第一部は質問コーナー、第二部は空き缶集めに関する実演、第三部はそれぞれが語るホームレス時代とメッセージ。最後は会場と一体となり「ひょっこりひょうたん島」を歌って踊るという構成となっている。
そして六月。最初の公演が決まった。久留米の小学校が呼んでくれることになった。「おけいこ」に力が入る。公演日が迫ったある日学校から電話があった。校長がホームレスということで難色を示しているとのこと。担当の先生もあれこれ動いてくださったが公演は中止となった。「公演中止」。これが生笑一座の船出であった。
八月。私は県の人権教育大会に呼ばれていた。大会主催者であった福岡県同和教育研究協議会の和多則幸先生が先の事情を知って、私の講演の中で生笑一座を上演しては、とご助言くださり、ついに第一回公演が決定した。会場はアクロス福岡シンフォニーホール。二〇〇〇人の前での公演となった。心臓が飛び出しそうな緊張の中、でも皆頑張った。
和多先生は「おけいこ会」に参加されるようになっていた。どうしたら子どもたちに伝わるかなど教師としてアドバイスをいただいた。この先生は一座の産みの親の一人である。公演の後、以下のメールをいただいた。「知志さま。『生笑一座』の公演デビューとても意義深かったですね。昨日も今日も、ふとした瞬間、バイオリンの音とともに、頭の中で房野さんの『しゃぼん玉』の歌が聞こえてきます。奥田さんとの出会いが生笑一座のみなさんとの出会いにつながりました。生笑一座のデビューに向け、参加させていただく中で、たくさんの方に出会うことが出来ました。僕の宝物がたくさんできました。西原さんと病気や入院時の話になりました。ガンの経過をたずねると、とても良好だということで安心しました。時々の検査もあるけど、『みんながついてくれてるから』と、とてもにこやかに答えてくださいました。ぼくも二〇一一年八月末から半年間の、無菌室での入院生活を思い出し、西原さんの言われたことがよくわかるような気がしました。ガラス越しの面会ではありましたが、『僕の周りに、こんなに人がいたんだ』と気づけたことは、僕自身のエネルギーにもなりました。二人で歩きながら、『お互い身体に気をつけて、元気に頑張りましょう』と笑顔で励ましあいました。房野さんや松尾さん、松葉さんともたくさんお話しすることができ、「生きる」ということや「つながる」ということ、「助けること、助けられること」の意味など、たくさんのことを学ばせていただきました。教職に就き、「先生」と呼ばれて久しくなりますが、「まだまだだなあ」と恥ずかしくなるばかりです。これからも、サルではなく「人間」になるために、たくさんの出会いの中で学んでいきたいと思っています。」 あれから三年が過ぎた。和多先生は、その後も一座に関わり続けて下さっていた。
二〇一五年四月二二日。和多先生は五二年の生涯を閉じられた。白血病が再発したという。あまりに急な知らせに絶句した。葬儀には一座で参列した。和多先生の笑顔の写真が会場正面に掲げられていた。さびしかった。和多先生、ありがとうございました。これからも一座を見守ってください。僕らがんばります。
スタートでの躓きは生笑一座にとってある種、宿命的なものを感じさせた。「一筋縄ではいかない」という現実を生きてきた人々の一座なのだから、こんなこともあるといったところか。一座のメンバーは嘆くことも意気消沈することもなく、その間おけいこに励んだ。和多先生との出会いも大きかった。大きな集会、しかも、もともと対象としていた小中学校の先生二千人の前で第一回公演が出来たことは幸いだった。おかげでその公演を見た先生から公演依頼がくるようになった。
その年の一二月。若松の北九州市立江川小学校から呼ばれた。子どもたちは、目を輝かせながら一座の話に聞き入った。公演の後、教室に行き一緒に給食をいただく。帰りには授業時間であるにも拘わらず正門まで子どもたちが見送ってくれた。それを教師たちが笑顔で見守る。なんとおおらかな学校か。子どもにサインを求められ恥ずかしがりながら名前と住所書くおじさんたち。満面の笑み―笑える日は現に来ていた。
生笑一座の公演を依頼される学校の中には、事前学習をしたいがどうしたら良いかとの相談が入ることがある。しかし、「事前学習はしないでほしい」とお願いしている。この一座は「学習」というよりも「出会いの授業」と考えているからだ。知識としてホームレスや貧困について学ぶことは大事だが、しかし、学びと出会いは違う。いやむしろ、本当の学びは出会いの中にこそあると思う。あるいはことばや知識は、出会いによって肉付けられなければならないと思うのだ。「ことばは肉体となってわたしたちのうちに宿った」(ヨハネ福音書一章)。だから生笑一座は、事前学習をお断りしている。
ただ、江川小学校の場合は一か月後に事後学習に再訪問した。その日はこちらも何の準備なしの出たとこ勝負のやり取りとなった。対話を楽しむ。それが出会いを核とする学びなのだと思う。子どもたちから思いがけない質問が飛び出す。冷や汗をかきながらおじさんたちは応えていた。
年が明け元旦の朝。新年礼拝の準備をしていると玄関のチャイムが鳴った。ドアを開けると一座のメンバーである西原宣幸さんが立っていた。年賀状の束を持っておられた。江川小学校の子どもたちからの年賀状だ。「おいら、こんな沢山年賀状もらったの、はじめてよ」と笑っている。しばらくするとまたチャイムが鳴った。一座の松尾壽幸さんだった。やはり手には年賀状。「支える人と支えらえる人」―そんな固定された区別は必要ない。一座のメンバーが子どもたちを勇気づけ、子どもたちが一座のメンバーを元気づける。出会いとはかくもフェアーなものなのだとつくづく思わされた。
公演の終わりに一座のポストカードを配る。これは「出会った責任」ということについて皆で議論する中で生まれた。公演では「助けてと言って良いんだ」とかつてそれが言えなかったメンバーが自分を振り返りながら子どもたちに語りかける。でも、それを聞いた子どもが「助けて」と言ってきた時、一座はどうするんだ、ということが問題になった。ポストカードには一座の住所が印刷されている。電話番号もメールアドレスも。QRコードがあり最近の携帯ならカメラでピッとするだけでメールが打てる。これを配るには少々勇気が必要だ。しかし一座は「出会った責任」を果たそうとしている。これも出会いの授業である所以だ。
二〇一三年三月北九州抱樸館の建築が始まろうとしていた。このプロジェクトは二〇〇九年に始まっていた。一九八八年から始まったホームレス支援は「新しい地域福祉の拠点をつくる」という段階に入ろうとしていた。活動開始二〇年を経て自立者は千人を超えていた。一方で路上者数は二百人となり、ピーク時(二〇〇四年五百人)の半数となっていた。まだまだ路上のいのちに対する支援の手を緩めるわけにはいかないが、一方で自立しハウスレス状態(経済的困窮)は脱してもホームレス(関係的困窮)状態が続く中で地域生活を続ける方をどのようにして継続的に支援し続けるのかが課題となっていた。すでにNPOでは、二〇〇五年には地域生活サポートセンターが開設され伴走型支援が実施されていたが、訪問にも限界があり、支援の拠点となる施設が必要となっていた。また、何よりも自立後の生活の中で一人暮らしが困難となった方に対するケア付きの住宅、あるいは看取りの施設の必要を感じていた。
折しも二〇〇九年三月当時の政府が全国民に対して「定額給付金」を支給することを決定した。NPOとしては、すぐに記者会見を開き北九州市民に対して「給付金(一万二千円)の約一割(千円)を社会還元しよう!」と呼びかけた。約五年かかったが最終的に六千万円の資金が集まった。この市民の応援を受けて抱樸館北九州は、いよいよ着工することとなった。
しかし、地域に対して計画を発表するやいなや建設反対の住民運動がおこった。二〇一三年五月から一二月まで一七回の住民説明会を開催するも理解を得ることは難しかった。そのような中で説明する自分のことばの限界を感じていた。ホームレス状態にある方々の実情や自立支援の意義などを説明するが、やはり実際にホームレス経験のない僕のことばはどこか宙に浮くような感じがしていた。毎度「謝罪しろ」と迫られ、頭を下げるが、当然そんなことでは収まらない。そもそも何を謝罪しているのかわからなかったが、謝って建つものならばと頭を下げた。しかし、当然そのような「心のこもっていない謝罪」など通用しない。行き詰まりの中で時間だけが過ぎて行った。
自らのことばの限界と向き合う中で、当事者のことばが必要だと考えていた。そこで自立者の互助会である「なかまの会」の世話人であった西原宣幸さんと下別府為治さんにお願いすることにした。西原さんは一一年間、下別府さんは五年間の野宿経験をされている。まさに死線を越えた二人に話してもらいたいとお願いしたのだ。考えてみるとこれが「生笑一座」の原型となった。
不特定多数の前で自分の一番しんどい時の経験を話すには覚悟がいる。偏見や差別に基づく発言が飛び交う住民説明会。二人が深く傷つくようなことになるやもしれない。しかし、二人は「わかりました。お話ししましょう」と引き受けて下さった。
会場には五〇名程の住民が集まっておられた。二人の話が始まった。野宿になった経緯、当時の暮らし、死んでしまおうと思った日のこと、そして自立を決意したこと。会場は静まりかえった。二人のことばは、決して流暢ではなかったが、事実によって受肉化されており、容易に否定することなどできないほどの「威厳」に満ちていた。話し終えると会場から拍手が起こった。「よかった」。二人は笑顔だった。
だが、その後会場の空気は一変する。反対の先頭に立っていた方が「あれは幸せの旗じゃないですよ。それに、あなた達のようなまともな人は良いんですよ。しかし、ホームレスの大半はまともじゃないでしょう。そういう人に来られたら困るんですよ」と語り出した。二人から笑顔が消えた。「やっぱり駄目か」と僕が意気消沈しかけたその時、西原さんが再び語り始めた。「私は、先ほどお話ししたように十一年間野宿をしていました。その間何度も支援機構のみなさんが支援を申し出られたのに、それを断り続けていました。やけっぱちにもなっていました。まともじゃないと言うなら、まさに私はまともじゃない人間でした」。会場は、静かになった。その後、いつも通り「ともかく奥田は謝れ」ということになって「すいません」と謝って解散となった。
今回の施設は主に自立後の終の棲家をめざし、同時に地域に暮らす困窮・孤立状況の方々が支え合いと交流のできる地域福祉の拠点を創ることを目的としていた。実際に入居される方の多くは自立後十年以上たった方々であった。だが、そのことを説明しても「今は地域で暮らしていても所詮ホームレスじゃないか。危険だ」という発言が飛び出す。「所詮元ホームレス」。このことばは、冷たく重く私たちに、そして何より当事者にのしかかった。
さすがにその夜は眠られず、西原さん、下別府さん、そしてNPOのスタッフたちとやけ酒となった。飲み過ぎた私は「野宿したことがある。それの何が悪い。何が違う。なんで差別する。所詮ホームレスとはなんだ。誰が一体まともなんだああああ~」と号泣した(らしい・・・あまり覚えていない・・・)ので谷本牧師、岩崎牧師までもが心配して駆けつける事態となった。
実は、生笑一座は、あの説明会の半年後に誕生した。それには、あの日が大きく影響している。ただ、それは「元ホームレスだけれどもまともです」とか「元ホームレスだけれどこれだけやれます」ということを証明したかったのではない。あの日、私は「当事者のことば」のすごさを実感したのだ。二人の話しは、ホームレス経験のない私には到底語ることの出来ないことばであり、しかも、死線を越えてきた二人だけあっておおらかで優しさに満ちていた。
「所詮元ホームレス」ということばは、差別的であると同時にホームレス状態に陥ったことをマイナスとだけ捉える立場が明確に示されている。確かに喜んでホームレスになる人はいない。出来ればそうならない方が良い。しかし、ホームレス時代を生き延びた人には、「特権的なことば」、あるいは「能力」のようなものがあると私は思っている。私には見えない世界が彼らには見えており、私には語ることの出来ないことばを彼らは持っていた。あるいは、たとえ私が同じことばを語ったとしても、その意味するところや深みは違うものとなる。これはすごいことではないか。「元ホームレスだけど話せます」ではない。「元ホームレスだから子どもたちに生きることについて語ることができる」のだ。ホームレス経験をキャリア化する。ホームレス経験は能力、強みなのだ。それが生笑一座である。
ホームレス経験はキャリアである。言い過ぎだろうか。しかし、もしそうであるならば隠したり否定したりするのではなく、役立てることができる。いや、現に生笑一座の場合は、役に立っている。これまでホームレスと言えば支援を必要としている「要援護者」、あるいは助けられる側の「弱い人々」と認識されていた。支援現場では、往々にして「助ける人」と「助けられる人」が明確に分かれていた。そして「助ける人」は常に元気で「どうぞ、どうぞ」と言っていたし、良いことをしているという自意識はその人を元気にさせた。だが「助けられる人」は、当初は感謝できても、常に「ありがとう、すいません」と言わされ続け、だんだんと元気がなくなっていく。
東日本大震災後、「絆」ということばが全国を席巻した。しかし、もしその絆が元気な人がかわいそうな人を支えるというものに過ぎないなら、それは本当に絆と言えるか。絆は、常に平等性を担保しなければならない。あるいは相互性や可逆性を内包しているからこそ絆なのではないか。すなわち助けられたり助けたりする相互性や、あるいは助けられた人が助ける人になれるという可逆性があるかが課題である。
生笑一座は絆の具現化である。それまで支えられる側であったおじさんたちが、今度はその経験を持って子どもを支える側に回る。そして、さらに前述の通り、公演で出会った子どもたちからの年賀状は更におじさんたちの生きがいとなる。生笑一座は、そのような相互性が担保されている。
助けてと言う叫びに誰かが応えてくれたなら、自分は尊重されていることを実感できる。自尊感情である。しかし、それだけでは人は本当には元気にならない。誰かから助けてと言われた時、自分は必要とされていると実感できる。自己有用感である。自尊感情と自己有用感の両立が生笑一座なのである。
社会は、舞台である。社会的排除は、いわば舞台から降ろされた状態であると言える。それが舞台である故に舞台に上がった人は、誰でもセリフが与えられ、役割を得る。また、一人芝居という舞台もあるが、基本的にはより多くの登場人物が登場する方が楽しい。さらに、当初悪役として登場した人が、いずれ味方になるという展開は、最も舞台を盛り上げる。「反対住民」が支援者になる日が来たならその舞台は大いに盛り上がることになる。良い社会というのは、良い舞台である。この社会において「野宿経験」というキャリアを武器に舞台に立つ名優がいて良いではないか。他の誰にも演じることができないその役どころを見事に果たしていく。それが生笑一座である。
一座のメンバーである西原さんは言う。「ホームレスに戻りたいとは思わないけど、ホームレスをしたことは無駄じゃなかったと思う。誰かに助けられるありがたさを知ったし、誰かを助ける喜びも知った。それは、ホームレスをしたからだと思う」。これは、彼にだけ与えられたセリフである。
公演内容を一部紹介する。唯一の女性座員の房野幸枝さんは一座の歌姫である。彼女は子どもたちに静かに語る。
「しゃぼん玉のうた、知っていますか?このうたの歌詞をつくったのは野口雨情(のぐちうじょう)さんです。歌詞をちょっと読んでみましょう。『シャボン玉飛んだ、屋根まで飛んだ、屋根まで飛んでこわれて消えた。シャボン玉消えた、飛ばずに消えた、生まれてすぐにこわれて消えた。風、風、吹くな。シャボン玉とばそう』。ちょっと悲しい感じがしますね。じつは、雨情さんの娘さんは、生まれてすぐに死んでしまったのです。『生まれてすぐにこわれて消えた』というのは、自分の娘のことでもあるのです。野口雨情さんは、こどもが死んで、とっても悲しかったのです。みんなはどうかな。死んだら悲しい。だれかがとっても悲しい思いになるよ。死んだらいかんよね。生きようね、生きていれば笑える日が来る。
実は、わたしも住む家がなくなってしまったことがあります。そのままだったら死んでしまったかもしれません。ほんとうに困りました。そのとき思い切って『助けて』といいました。そしたら、何人もの人たちがちゃんと助けてくれたのです。困ったときは『助けて』と言おうね。そしたらきっと大丈夫。生きようね」。そして彼女は「しゃぼんだま」を歌う。涙を流す子どももいる。
子どもが「助けて」と言わない時代となった。誰にも「助けて」とも言わぬまま子どもは死んでいく。私は最近新学期が来るのが怖い。新学期を迎える度に、また子どもがいのちを断つ。この国の最も深い闇だ。
一座の下別府為治さんは言う。「おじさんは一人でなんとかすると思って生きてきました。そして、ある日どうしようも無くなくなりました。ホームレスになって毎日大変でした。ある日道で倒れ病院に運ばれました。そうしたら、お医者さんやボランティアの人が来てくれて助けてくれました。自分一人で頑張るしかないと思っていましたが、でもこの世の中には助けてくれる人はいたんです。助けてと言えた日が助かった日でした。だから助けてって言っていいんです。きっと誰かが助けてくれます。がまんしないで助けてと言ってください」。この子らは一体どんな思いでこの話しを聴いているのだろうか。
なぜ子どもたちは助けてと言えないのか。様々な理由があると思う。しかし、大きな原因の一つは私たち大人が「助けて」と言わないからだと私は思う。私たち大人は少しがんばり過ぎているのではないか。「がんばればなんとかなる」と言って歯を食いしばり「助けて」を封印してしまった大人社会。「自分だけの力で生きる」。それが立派な大人だと子どもたちからは見えているのかもしれない。さらに自己責任を強調することで「助けない理由」にした大人社会がまるで「正しい社会」であり、その一員となることが「賢い社会人」であるかのように見えているのかも知れない。そんな風に私たち大人が子どもたちに思わせているのであれば、子どもの死の責任は私たち大人にある。
「誰の力にも頼らず自分の力で生きていく。それが立派な大人と言うものだ」。でも、それは本当か。子どもたちには、そう見えているのかも知れない。
「正直に言いなさい」。時に大人たちは、子どもたちにそう迫る。「正直に言ったらゆるしてあげる」。じゃあ、正直に言いたい。子どもたちに伝えたい。「実はね。僕ら大人も誰かに助けてほしいと思いながら生きているんだ。毎日結構つらいことがある。自分でなんとかしたいと思うけど、なかなかそうはいかない。さらに、悪いことに大人はそれを正直に言えなくて、嘘をついてがんばってしまう。大人の世界では負けを認めると『負け組』なんて言われてしまう。でもね、実は僕ら大人も一人じゃ生きてはいけないんだ。でも、それを認めることが出来ない弱い存在なんだ。独りでがんばって、助けても言えず、気づけばホームレスになったりして、それでも助けてって言えずに何年も公園の片隅で独りぼっち頑張ったりしている。寂しかった。つらかった。そして、ある日、勇気を出して『助けて』 って言ってみた。それが本当の大人の姿なんだ。だから、君たちに頑張れって言うことは、本当は辛いんだ」。生笑一座は、この事実を正直に子どもたちに伝えている。作り話でも、お芝居でもない。ただ正直に。
「助け、助けられる」ということは人間の本質だ。これを拒絶し、ごまかす社会はもはや社会ではない。ひとりでは生きていけない。そもそもひとりで生きていない。それが真実なのだから、人は社会を必要としたのだ。
死さえも覚悟した人々が、最後の最後「助けて」と勇気を出して言った。恥ずかしいことなんかじゃない。それが人間だ。本当の誇り高き大人とは、助けてと言える大人。それこそがとても美しく素敵であり、人間らしいと思う。だから生笑一座は素敵だ。人が人であり続け、社会が社会であり続ける。そんな当たり前のことが揺らいだ現代において生笑一座の果たす役割は決して小さくはない。かつて死んでしまおうと思った人が、今では誰かのために生きている。笑っている。生笑一座そのものが希望なのである。
公演の最後は「ひょっこりひょうたん島」である。子どもたちと歌って踊る。「丸い地球の水平線に、何かがきっと待っている。オウ!」。そうだ、何かが待っているんだ。
「苦しいこともあるだろさ(ハイ)。悲しいこともあるだろさ(ハイ)。だけど、僕らはくじけない。泣くのはいやだ、笑っちゃおう。進め!」。泣けるなあ~。生きていれば出会える。生きていればいつか笑える日が来る。嘘じゃない、現にあのおじさん達は笑っているではないか。だから勇気をだして「助けて」と言おう。とにかく笑いたい。楽しいから笑うんじゃない。それを待っているとなかなか笑えない。とにかく笑う。笑っていると楽しくなるんだ。「笑っちゃおう!進め!生笑一座!」生笑一座は、厚生労働省の自殺対策のプロジェクトに選ばれ、活躍中である。
以上が、生笑一座誕生のいきさつである。あなたは、もう生笑一座を観たか!あなたは笑っているか!
おしまい