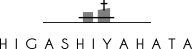2025/05/18
5/18巻頭言「調べられることは覚える必要はない―AIの時代を生きる『支援者』」最終回
「AIが支援計画を作るようになれば支援員は不要になる」と慌てる人も出てくる。そうはならないと思う。それどころか支援員は今後『最も大切な仕事』に集中することになる。支援員の働きは支援計画の作成だけではない。それよりも支援計画に対して相談者ご本人が『その気』になるかどうか、その点において支援の意味が問われる。相談者の多くがギリギリの状態でやってこられる。中にはもうすでに意気消沈を通り越し絶望している人もいる。そういう人がもう一度生きる意欲に火を灯すには何が必要か。これまでも実はそのことが何よりも重要だったはずだ。支援計画がどれぐらい緻密で正しくてもご本人が『その気』にならないのなら、それは単なる紙きれに終わる。
支援員の最も大切な働きはご本人に伴走し、その思いを想像すること。その人の悲しみや苦しみ、どうやって生きてきたのか、その思いを理解すること。共に苦しみ共に泣く、そして共に笑う。早々に問題解決に至らなくても大丈夫。支援計画などAI君が瞬時に書き換えてくれる。これまでみたいに支援員の「徒労感(せっかく支援計画創ったのに・・・)」は半減する。これからは共に歩み、共に生きることに集中できる。つながりの中で人は生きる力を得る。そのために全力を注げる。支援員の仕事は「人の思いの部分」に集中するという最も大切なことに集約されていく。
そういうことになると『座る位置』も変わっていく。これまで支援員は相談者の向かい側に座りアセスメントを実施し、支援計画を作成することが第一の仕事だった。今後は支援員と相談者が横に並び、AI画面の前に座りAIが提示する支援計画を一緒に眺めるようになる。そして「ああでもない、こうでもない」とAIをネタに話し合う。目の前の支援員が作ってくれた支援計画に「ケチ」を付けるのは勇気がいる。だが所詮AIは機械(技術)に過ぎない。遠慮なく「なんか違うなあ」と文句が言える。支援計画がつまらなく『やる気』が出ないものなら「このAIわかってないよね」と二人で悪口を言う。そういう反応を見ながら一緒に支援計画を練り上げていく。そうなれば従来の支援する側、支援される側という枠組みも融解し、もっとプレーンな関係、共に生きる者同士の関係が成立する。
「調べられることは覚える必要はない」。AI時代を生きて行くこれからの世代においてこのことばの意味は深い。福祉分野のみならず、学問、教育、受験などあらゆる分野でこれまでの在り方が変わっていくだろう。AIだの、DXだの、言葉の意味もほとんど理解していない私がこんなことを言っているのはどうかと思うが、AIの登場が人を蔑ろにし、民主主義の崩壊を来たらせるようなことになるのではないか、文明を破壊するのではないかとの心配がある中で、私はひとえにそれらが人間性が深まる契機となることを願って止まない。
おわり